先生は 『摩擦を使えば、仕事を全部熱に変えることができる』 と言っていましたが、正確には 『仕事が内部エネルギーに変わる』 としか思えないんですが...?
そのとおりです。 ただし、その内部エネルギーの増加がどのようにしてもたらされたか?を考えてみてください。
粗い机の上に置かれた(断熱)物体を押して移動させる場合を考えます。 物体を押す人は確かに摩擦力に抗して 「力×移動した距離」 の仕事をしています。 しかし、机から見れば確かに力(物体に及ぼした摩擦力の反作用)を受けますが、移動はしていませんから 「力×移動距離」 というマクロな意味での仕事をされたとは言えません。 しかし、熱くなることは確かですから分子運動レベルでの仕事、すなわち熱の形でエネルギーを受け取ったとしか言いようがないのです。 つまり、 仕掛けた側は仕事のつもりでも受け取った側では熱、 ということになります。
それでは、固体摩擦ではなくジュールの仕事当量の実験装置のような場合はどうでしょう。 この場合も同じことなんですが、気持ちが悪ければこのように考えればいいでしょう−−−−−恒温槽に浸けられた金属製の箱の中に粘性の強い油を充填し、密集した羽根車が付けられた軸が油の中を外からの仕事によってゆっくりと回転出来るようにしておく (油制動装置) 。 この装置に外から仕事を加えてやれば油の温度が上がります。 この装置の温度 \(T\) を (もちろん体積 \(V\) 、したがって内部エネルギー \(U (T,V)\) やエントロピー \(S (U,V)\) も) 一定に保っておけば、仕事によってもたらされたエネルギーは全部、恒温槽に熱となって出て行く.....
53ページの例2 (等エントロピー変化における内部エネルギー極小原理の例) は、 自由に動ける断熱壁 (ピストン) にこのような制動装置を接続して、 ピストンの両側各部分系内の圧力が常に一様 (一定ではなく一様) に保たれている程度にゆっくりと (=準静的仕事すなわち等エントロピー的に) ピストンが動くようにした、 と考えれば文句はないでしょう。 この場合はシリンダ内の気体と油をあわせた系を考えれば、 ピストンに取り付けたヒモを介しての仕事は内部作用ですから、 外に対しては 「仕事なし」 です。 油は温度も体積も変わっていないからその内部エネルギーやエントロピー変化を考慮する必要はありません。 したがって、 シリンダ内の気体について 「等エントロピー、 仕事なし」 バージョンの判定条件 「 \(\mbox{d}U \lt 0\) 」 を適用することができます。
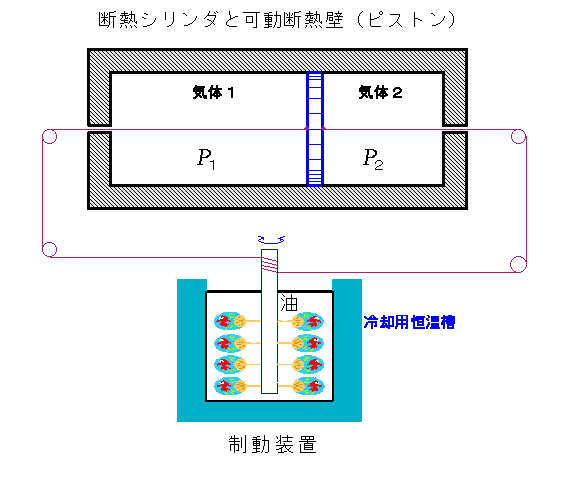
これを、 シリンダの中の気体だけを対象とし、 「外からの準静的仕事を行う」 と考える場合は、 ピストンの任意の方向への移動が可能、すなわち可逆です。上の制動装置をつけた系の場合は、 油を冷やしたらピストンが元に戻って圧力差ができるというようなことは絶対に起きません。
講義ノートのようにピストンと容器の壁の間の固体摩擦で準静的操作を実現しようとしたら、 「摩擦があるなら有限の圧力差があってもある程度小さければ、 ピストンは止まってしまうのではないか?」 と鋭いつっこみを受けました。 それに 「断熱シリンダである」 といいながら 「シリンダで摩擦熱が発生する」 というのもひっかかる人が出てくるのはあたりまえでしょうね。
油の粘性による制動なら原理的には無限小の圧力差でも動き始めます。 端的に言えば 「静止摩擦係数は0」 です。 流体が運動し流体内に速度勾配ができてはじめて粘性摩擦が働くようになるのです。 また、 シリンダで発生した熱は直ちに外部へ放出してしまうことを前提にしています。
ここで、 このシリンダ (または先の制動装置でもいい) で発生した熱が放出されるのではなく、 全部気体に戻されるとしたらどうでしょうか? この場合、 ピストンの両側各部の 「どちらに どれだけずつ 戻されるか」 によって各部分系の内部エネルギー変化量が異なります。 しかし、 この配分を決める原理は何もありませんから、 この場合にはピストンの平衡位置は、 それぞれに配分される熱、 したがってエントロピー変化がいずれも正という範囲内で 不定 ということになります。
ピストンが外部に接続されず摩擦なしで自由に動く場合でも、 気体の内部摩擦 (粘性)によって熱が発生(エネルギー散逸) しピストンの振動は速やかに止まりますが、 この熱発生はどのようにピストンが運動するかに依存し、 熱力学的条件だけでは決めようがないのです (「断熱ピストン問題」)。
(余談) 以前はこういうのをレポートとして出してくれる人がよくいました。 講義ノート35ページの 『準静断熱等温非可逆過程』 の例も感心した一つです。

